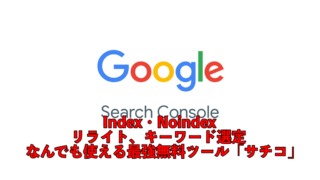インターネットビジネスで自分の力で稼ぐために必要なスキルとして「ライティング」が挙げられます。
しかし「ライティング」といっても、
- SEOライティング
- コンテンツライティング
- コピーライティング
- セールスライティング
などなど、定義も言葉も違う”○○ライティング”があるのも事実です。
今回の記事では、インターネットビジネスにおいて、自分の力で稼ぐための「ライティング」にはどんなものがあるのか、どのようにそのスキルを身につけていけば良いのかなど、わかりやすくまとめていきます。
今回の内容
Miyaが思う大事な3つのライティング力
冒頭でも言いましたが、「ライティングは大事だよ!」なんて言われても、調べてみると”○○ライティング”なんてたくさんあるわけで、何を学べば良いか正直わかりませんよね。
そこで、僕が思うインターネットビジネスで役に立つ(大事な)ライティングを紹介します。
よく使っているライティングと思ってもらっても構いません。
それが以下の3つです。
- ブログアフィリエイト向けのライティング
- 自分のファンになってもらうためのライティング
- 商品・サービスを売るためのライティング
色々な言い方はありますが、ここでは専門用語を使わずに以上のような言い方を敢えてしています。
それぞれ解説していきます。
ブログアフィリエイト向けのライティング

ここでのブログアフィリエイトも定義は難しいのですが、ここでは以下のように定義したいと思います。
- アドセンスや他社の商品・サービスを売るブログ
- お客さんを選ばずとにかく多くの人に見せるためのブログ(アクセス重視)
インフルエンサーとは真逆の立ち位置にいるブロガーだと想像してください。
この種のブログはインフルエンサーとは違った戦略でお金を稼ぐため、大事なライティングスキルは主観性よりも客観性になってきます。
もしあなたが、「雑記ブログや特化ブログ(つまり副業レベル)で稼ぎたい」というならばこのブログアフィリエイト向けのライティングをいち早く身につける必要があります。
もう少し掘り下げて、「ブログアフィリエイト向けのライティング」とは何か説明すると、それは一言で言えば、主観性よりも客観性です。
雑記ブログや特化ブログを運営する人(顔出しなし・権威性ないとして)のブログの内容を見てみると、客観性ではなく主観性の強い文章になっていたりします。
あなたは自分のキャラや権威性をブログに載せていないにもかかわらず、ブログの内容を見ると個性の強い文章が表現されていると読者との温度感が生まれ、読者が離れていく原因になります。
主観性が強いブログによく見られる特徴として、
- 「!」がやたら多い
- おかしくもないのに「笑」「wwww」が使われている
- しゃべり言葉そのままを文章に書いてしまう
などが挙げられます。新聞を書くくらいの気持ちで十分です
自分のファンになってもらうためのライティング

ブログアフィリエイト向けのライティングとは真逆の立ち位置で、自分のファンになってもらうためのライティング力が必要となります。
「どうやって文章だけで自分のファンになってもらうんでしょうか?」
なんて疑問が浮かぶかもしれませんが、読者があなたに求める具体例を何個か挙げてみたいと思います。
- 職業
- 性別
- 年齢
- ライフスタイル
- 過去のストーリーや実績
などなどです。
「ブログアフィリエイト向けのライティング」とは真逆であなたの主観や考え・意見を述べることで読者があなたのファンになってもらうことが可能になります。
逆に客観的なことばかり述べてしまうと、ファンになってもらえないどころか、他と差別化できずにあなた自身が埋もれてしまいます。
商品・サービスを売るためのライティング
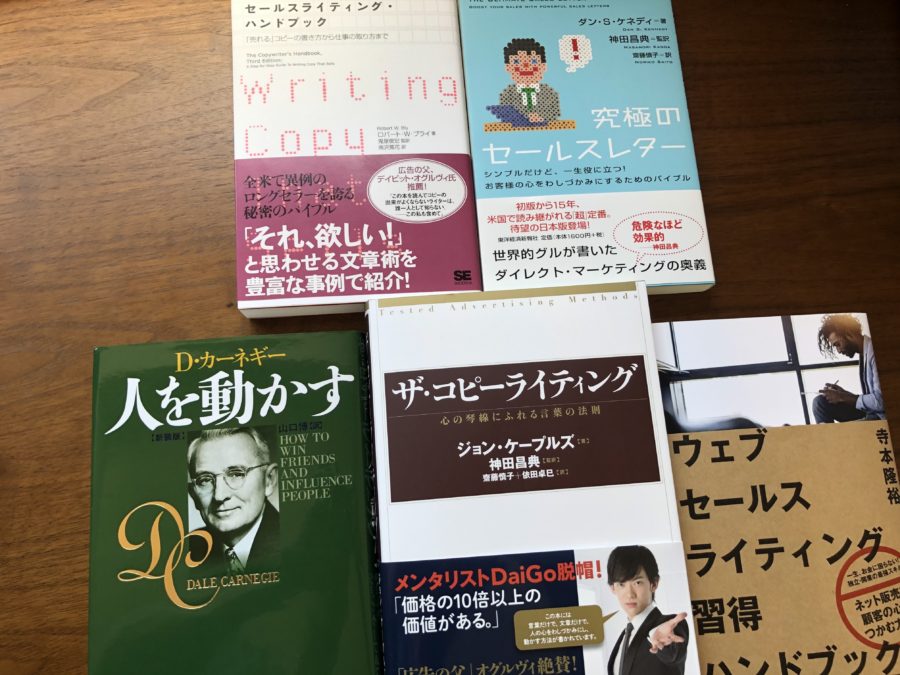
最後に解説するこの「商品・サービスを売るためのライティング」は、これまで説明した2つのライティングの間をとったスキルといっていいでしょう。
主観的な情報だけでも商品は売れず、客観的な情報だけでも商品は売れません。
そして、主観と客観のバランスを文章に加えて、大事なポイントは、
お客さんの購入を妨げる障害を一つ一つ取り除いてあげること
これは文章だけではありません。リアルビジネスの世界でもお客さんが一つでも商品・サービス(機能面や価格も含めて)に不安があれば購入に結びつけることができません。
特に文章でモノを売る世界では、お客さんと対話ができないため、「全ての不安を想像する力」がかなり必要になってきます。
小手先のライティングスキルより、相手の立場を想像することが一番大事だと言えます。
まとめ
今回はネットビジネスにおいて、Miyaが思う「身につけるべきライティング」を解説してみました。
今回紹介したライティングは言い換えれば、「SEOライティング」「コンテンツライティング」だったりと言われることもありますが、ここではあえてそういった専門用語を使わずに場面に応じた使い分け、そして書き方を解説しました。
それぞれの身につけ方などはまた別記事にまとめていますのでご覧になってください。
最後までご覧いただきありがとうございました。